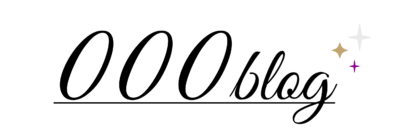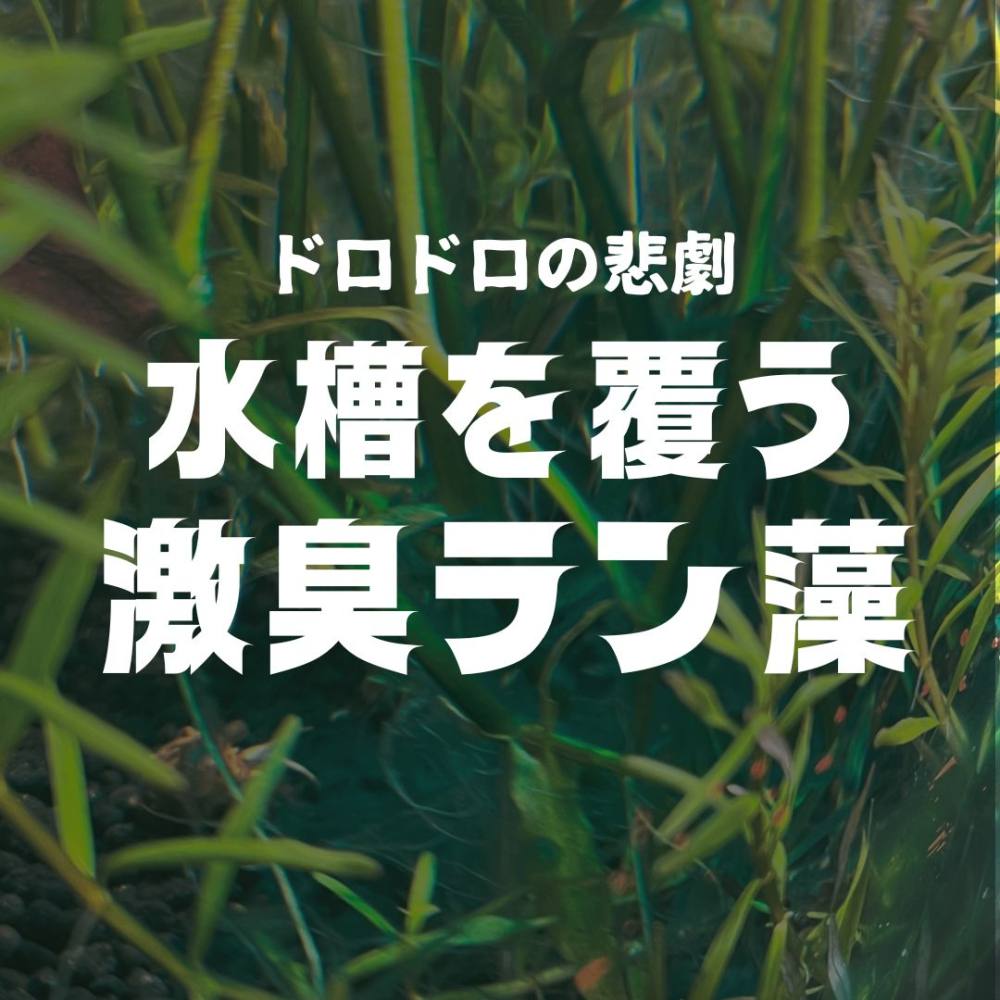育成中のコケテラリウムに大量の白い虫が発生したので、植え替えを行いました。発生した原因と虫対策について植え替えを行いながらお話ししたいと思います。
状況と経緯
コケの種類

自宅のタマゴケは2024年の秋頃より植え付けを行っているので約1年が経過しています。着生に時間がかかりましたが、最近は小さな葉がポツポツと芽吹き始め、ゆっくりとではありますが、順調に育っている様子でした。
虫の発生時期と生態
2025年の夏はワインセラーに保管し気温を安定させた状態で保管していました。
ワインセラーで保管していた理由は適度な温度調整が可能なことと、ガラス扉になっているため光合成を行えるように用意したものです。他にもホソバオキナゴケやホウオウゴケ、水草を育てていますが、全て同じ環境下で育成していました。
しかし、7月中旬頃にタマゴケの容器にのみ、体調0.3mm~0.5mm程度の白く小さな物体を発見!
よ〜く見るとウネウネ動いたり飛び跳ねたりしています。
怪しい挙動と共存するコケ
こいつらの生態を見ておこうと、3ヶ月ほどそのまま育てていました。
どうやらコケに害はないようで、適温の環境下でこれまでどおり育っている様子です。
この状況から、当初はカビなどを食べてくれる、スプリングテール(益虫)というヤツかと思ったのですが、形やサイズが一致しない・・・。
味見をしたところ植物性のタンパク質そのもので、薄味の豆腐のような感じです。
それは冗談ですが、多分小麦粉とかについてるダニの一種じゃないかと考えています。
原因編

容器を観察してみよう!
容器の中をよく観察してみると湿った土に藍藻(らんそう)が発生していました。(そしてうごめくヤツら)
と、なると容器の中はコケ以外の生物も生息できるほど十分な栄養があるということだと思います。
快適な温度、潤沢な栄養。夏場にエアコンが効いた部屋でポテチとアイスを貪るように虫たちにとってはこれ以上ない楽園だったのかもしれません。
部屋中が臭い!?においのもとはなんと水槽でした。水草にべっとりとへばりついたドロドロの物体。そう、今回は藍藻の対策につい…
栄養過多の原因
植え付け時には生息場所に合わせ湿度を十分に保ちつつ、水はけの良い状態にしようと実験的に下層から川砂、赤玉土、砂利の順で植え付けていました。
主たる要因は川砂や砂利をいれたことだと思います。経験上、鉱物を入れると藍藻(らんそう)が発生しやすくなります。
植物は基本的にミネラル(鉱物)や土に含まれるリン、カリウムといった栄養素によって成長します。ただし、鉱物に含まれるミネラルは微量ですので、問題はその滑らかな表面にそれらが付着しやすいという点です。
下層に溜まった水分と蓄えられた栄養によってコケ以外の生き物もウネウネ、ピクピクと、育ってしまったのだと思います。
どこからきたの?
彼らが最初から混入していたのか、後からお引越しをされたのかは不明です。
ちなみに土や砂利はコケ農家さんから購入し、さらに下処理を行ったものを使用しました。容器は蓋付きの密閉タイプのものを使用しています。
とはいえ、室内であれば多かれ少なかれ”ミエナイナニカ”はどこかしこに潜んでいることでしょう。
どこから湧いたかはさておき、他のコケには虫は一切おらず、タマゴケの容器だけが住みやすい環境だったということは確かなようです。
解決編
虫が発生したタマゴケを植え替える上で、テラリウムとして適切な環境で育てるためにも対策しておきたいことは以下の4点です。
- タマゴケの掃除
- 栄養管理
- 鉱物の扱い
- 着生をすすめる
前回の植え付けでは虫の発生以外にも着生に非常に時間がかかったことも反省点です。ということで、テラリウムの衛生問題だけではなく、生育についても対策を加えたいと思います。
タマゴケのお掃除

コケが虫の棲家になっていると結果的に再発してしまうので、まずはコケを丸ごとお掃除します。
その際、密集しくっついているものはなるべく引き剥がさないようにします。コケは仮根や原糸体を土や周囲のコケに伸ばすことで次第にコロニー(群生)を築いていきます。彼らの結びつきを無理に引き剥がすと、コケは乾燥しやすくなります。
そこで土から優しく剥がしたコケを容器に入れた「炭酸水」に30分ほど浸しておこうと思います。虫の駆除には“炭酸水”が非常に有効だそうです。原理は炭酸水に溶け込んだ二酸化炭素で彼らを窒息させるというもの
地獄ですね
結果はご覧の通り、思った以上にたくさん住まわれてました。
土の下処理

使用する土は“水洗い”して余分な栄養と不純物を一気に洗い流してしまおうと思います。
使用する土はコケテラリウムでよく使用される赤玉土をメインにコケ用に配合されたものを使います。赤玉土は栄養価が少なくコケテラリウムにおいて、頻繁に使用される土です。
コケは本来、栄養をほとんど必要としません。栄養価の高い土壌では今回のようにテラリウムとしては汚れた環境を育ててしまうので、余計なものはいれずに清潔な土を使用します。
植え付け

下処理を行った土をしっかりと乾燥させたら植え付け開始です。
タマゴケのふんわり感を際立たせるため、山なりに土を盛り付けました。型崩れ防止に軽く霧吹きをかけて水分を馴染ませます。
コケを適当に乗せて、上から土をパラパラと乗せます。目土といって薄く土を載せておきます。コケを保湿し適度な水分量をキープしてくれます。目土をせず土の上に乗せるだけだと急激に乾燥がすすみ着生を妨げます。
栄養管理と着生まで
着生を進めやすいように、メネデールを希釈して霧吹きをかけます。
メネデールを使うメリットは即効性です。植物に対してダイレクトに浸透するので栄養の吸収効率がよく土に残りづらいものになっています。
そのため栄養過多を防ぎつつコケだけを健康に育てることができます。
着生するまでの管理
着生が進行するまでは適度に換気をしつつ、湿度をキープします。
着生前のコケは水分が抜けやすいので換気をする時はキムワイプを軽く被せて乾燥しすぎないように管理しています。
容器内の調湿は非常に重要で、水分が多すぎれば容器内に汚れは蓄積しますし、乾燥すれば着生が進みません。空気を循環させつつコケは軽く湿った状態をキープします。
まとめ
今回の例での虫の発生原因とポイントは「栄養過多、鉱物の扱い」の2点でした。
補足として、コケは養分をほとんど必要としないということは理解して育てていたので、栄養剤は基本的に散布せず育てていました。
それでも、今回のように生育環境をあやまると汚れが栄養が蓄積され、別の生態系に影響を及ぼすのではコケテラリウムのリアルなところです。
タマゴケの着生が進んだらまた更新しようと思います!