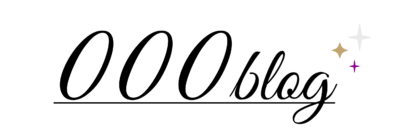最近のPOPMARTのLABUBU人気について、ぬいぐるみシリーズ発売当初から、LABUBUの動向を眺めていたPOPMARTユーザーの考えをお話したいと思います。
内容については、「製品としての価値、販売戦略とユーザー層、現在の人気について」これら3つのフェーズに分けてまとめています。今後の入手難易度や相場予測のヒントにしていただければ幸いです。
LABUBUの人気について

LABUBUについて
LABUBUとはPOPMART(中国のトイメーカー)から発売されている人気のブラインドボックスの一つです。同メーカーのシリーズの中でも他タイトルとのコラボが多く見られるのが特徴です。
中でもぬいぐるみシリーズは発売当初から売り切れ続出の製品でした。可愛いモンスター顔にモフモフ感が相まってキャラクターの個性を最大限に引き出しています。
昔、モンチッチというキャラクターが大ブームになったそうですが、どことなく面影もあり見た目からも人気の理由はうなずけます。
ぬいぐるみシリーズのヒットについて
POPMARTでは主にミニチュアのフィギュアを扱っており、それが派生してぬいぐるみシリーズがリリースされました。
LABUBUのヒットを機にスカルパンダやヒロノなどPOPMARTで人気のある他シリーズもぬいぐるみ化が進んでいます。しかし、抽選販売を繰り返すLABUBUぬいぐるみシリーズとは違い、その人気はやや緩やかな印象があります。
これはキャラクターコンセプトとぬいぐるみ化に乖離があることが影響しているのではないか?と考えています。
例えば私は数あるシリーズの中でもヒロノが飛び抜けて好きなのですが、それは感情表現が色彩や造形に反映された美しさを小さなフィギュアから感じられるからであり、単にヒロノの顔をつけた”ぬいぐるみ”はどこか味気なく感じています。
POPMARTのぬいぐるみであるから良いというわけではなく、LABUBUだったからこそという背景もあると考えています。
販売戦略とターゲット層

POPMARTの販売戦略
LABUBUの人気に関する大きな理由はPOPMARTの販売戦略にあると考えています。
POPMARTの製品はリリースされると即完売が大抵です。これはLABUBUに限ったことではありません。さらに、何が出るかわからないブラインドボックス形式によって”プレミア感”を増すことで、ユーザーの購買意欲に火を付けています。
POPMARTのターゲット層
POPMARTのフィギュアは「デザイナーズトイ」というだけあってアートとしての側面も持っています。フィギュアとはいえアニメや漫画とは違い、キャラクターに依存しないオシャレなものが多く存在します。
また、価格帯でいえば、「決して安くはないけど、コレクター製品にしては高くない」といった設定です。品質は担保しつつ、いわゆるフィギュアオタクといわれる人たちほど熱はない人でも手に取りやすいものになっています。
「アートカルチャー×潜在的なコレクター」
「ちょっとづつ楽しみながら集めていたら、コレクターに育っていた!」(笑)
こうしたライトなコレクター層を起点に販路を拡大しているのがPOPMARTの販売戦略ではないかと考えます。
過剰な人気について

こうした製品としての価値、販売戦略の土台の上に、芸能人の愛用といったわかりやすい宣伝効果を得たことで、現在の爆発的なヒットに至りました。ただし、その結果としてこれまでのような『”手に取りやすいプレミア感”』は失われつつあるように思います。
POPMARTブランドと運営スタイル
POPMARTは「ライトコレクター層」を起点にしつつも、純粋なコレクターにはより高価なものを、キャラクターが好きになった人には多様なグッズを用意するなど、ユーザーの変化するニーズにも柔軟に対応しています。
しかし、一方でそのどれもが「コレクター製品である」といった姿勢は崩していません。供給量を上手にコントロールすることで、一定のプレミア感は固く守っています。
その結果運営が不公平で杜撰であるといった印象を持たれることもあります。
店舗は関東を中心にその周辺に偏っており、かといってWEBストアの在庫が充実しているわけでもなく、受注生産やネット抽選ではなく、店舗限定抽選で列をなすなど・・・
これについては需要が増したことで、相対的に供給が制限されていると不満を持つ人が多くなったと捉えることができますし、さらにいえばPOPMARTのスタンス自体は特に変わっていないとも捉えられます。
大衆向けになりつつある矛盾
最近ではユニクロとのコラボTシャツなど大衆向けのニーズに応じた露出も見受けられます。既に受注販売も開始しているため、さすがユニクロ!といいたいところですが、POPMARTのブランド戦略とは離れたところにあるように思います。
サブカルチャーが大衆向けに変化したことによる影響についてはこちらの方のお話しがとてもわかりやすかったので、参考として載せておきます。
POPMARTファンの声と需給のアンバランス
これまでYOUTUBEなどでフィギュアを取り上げていた方達も”気軽に”楽しめなくなったことから、「気持ちが落ち着く」「悲しい」と発言される方もいます。私自身もその一人です。
前述でも書きましたが、大半のユーザーが「ライトコレクター」であり、潜在的なコレクターからコレクターへ育てていくのがPOPMARTの基本となるオペレーションだと考えています。
「ライトコレクターが求めるものは手に取りやすいプレミア感」
人気が増し、認知される機会が増えた分、POPMART特有の需給のバランスはその均衡を破りつつあります。さらに、こうした事態やその特性の重要度をPOPMART自身が自覚していなかったのかもしれない。ということが、大衆向けの人気にあやかったサービスの展開や変わり映えのないような運営スタイルから見受けられることに懸念を感じています。
まとめ
今回やや厳しめにPOPMARTの話を書きましたが、あくまでも個人の分析と感想によるものです。こういう見方もある。といったニュアンスで見てください。
では!考えをまとめていきます。
POPMARTは日本でいう森永のパルムやマウントレーニアのようにちょっといいものを気軽に楽しめるから人気があるものだと思っています。新しいものをつくり、程よいバランスで販売していくから、人気がある。競合の少ないエリアを選別し戦略的に戦う姿勢は非常に賢い企業のやり方だと思います。
こうした販売手法については、本来の持ち味ですのでLABUBUの人気が冷めてもバランスの良い品薄といった現状は変わらないと考えています。
ただし、需給のバランスにコントロールがなければ環境の変化によって相対的に供給過多、需要減少といった均衡を破る変化も起こります。
例えば如何にプレミアとはいえ転売により高値で取引されていれば、「ライトコレクター層」には刺さりません。さらにその現状を繰り返せば、「手に入らないもの」としてPOPMART自体にエネルギーを注ぐ人も減少します。連鎖的にブラインドボックスという楽しみにより育てられるはずのヘビーユーザーを取り逃す結果を招くことも考えられます。
このようなユーザーの取りこぼしは、長期的に見れば製品の売れ行きや相場にも影響を及ぼすでしょう。
現状のコントロールを失っている様相が私の思い込みの可能性もありますし、新たな販路を築くための挑戦過程でのエラーでしかないのかもしれません。
既に中国ではこうしたインフレに歯止めをかける動きもあります。これだけのブランドを生み出した企業ですので、新たな戦略により本当にPOPMARTが好きな人がコレクションを楽しめる日を楽しみにしています。
最近よく名前を聞くようになった中国発のキャラクター「LABUBU(ラブブ)」。ウサギ耳と牙(きば)が特徴的なモンスター型…